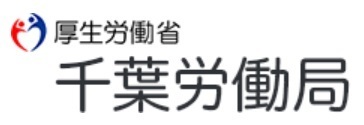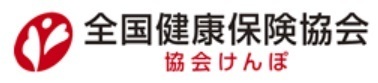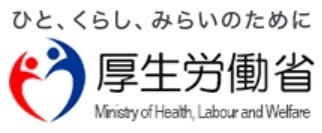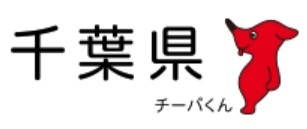助成金・労働問題に強い社会保険労務士(社労士)をお探しなら、千葉県千葉市の岡崎総合労務事務所へお問合せください。
よくある質問
 当事務所のサービスについて
当事務所のサービスについて
強みは何ですか?
勤務社労士時代を含めた15年を超える経験から経営者側の立場での労務問題解決に強みがあります。ホワイト企業を目指したい事業主様からのご依頼をお待ちしております。
費用を払ってまで社労士に委託するメリットは何ですか?
社労士は人事労務のプロフェッショナルです。高度な専門性をもって御社の人事部門をサポートいたします。特に当事務所は労務問題解決に強みがあるため、労働相談や就業規則作成で高評価をいただいております。
労務顧問契約をするメリットは何ですか?
単発の関与ではどうしても一時しのぎになりがちです。労務顧問契約により継続的に関与させていただくことで、法改正や御社の組織風土の変化にも迅速に対応することができ、長期的にホワイト企業を維持いただくことが可能となります。
給与計算だけの依頼もできますか?
もちろんです。労働法や社会保険の専門家であるためミスなく給与計算を行うことができます。給与計算が煩雑になってきたり、ミスが増えてきた場合は是非ともご依頼ください。当事務所への完全移行まで2~3ヶ月ほどの期間をいただいております。
千葉県外の会社でも依頼できますか?
原則、千葉県内をエリアとしておりますが近隣都県(東京・神奈川・埼玉・茨城)であれば受託させていただいております。なお、メール相談・電話相談は全国対応しております。
 人事労務Q&A
人事労務Q&A
30日分の賃金さえ支払えば社員を解雇してもよいのでしょうか。
社員を解雇するには相応の理由が必要です。
結論から言うとそれだけでは解雇することはできません。労働基準法第20条には「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」と記載されているため一見30日分の賃金さえ支払えば解雇できそうに思われます。
しかし、労働契約法第16条では「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」とし、客観的合理性および社会的相当性を求めており、それらを欠く解雇を無効としています。
よって、30日分の賃金を支払ったとしても解雇するだけの理由(客観的合理性および社会的相当性)がなければ解雇無効と判断されます。
労働組合から団体交渉申入書が届いたのですがどうすればよいのでしょうか。
初期対応で今後の方向性が決まります。記載内容をよく吟味しましょう。
突然の書面通知で驚かれたことと思いますが、絶対にやってはいけないのは無視や拒否をすることです。不当労働行為という違法行為になり、労働組合とのトラブルの元になります。団体交渉では誠実に交渉する義務は課せられていますが、要求事項に対して応諾する義務までは課せられていないため不必要に恐れることはありません。交渉過程で解決の糸口を見いだしていくようにしましょう。
まずは、相手に主導権を握られないためにも記載内容をよく吟味し、今後の対応を検討します。開催場所や開催時間・交渉人数などは初回の対応が労使慣行となってしまう場合もあるため安易な回答は禁物です。回答に不安がある場合は、早い段階で専門家に相談し適切な対応を心掛けるようにしてください。
社員が9人以下の会社は就業規則を作る必要はないのでしょうか。
義務ではありませんが労務管理上、作成したほうが望ましいです。
労働基準法では常時10人以上の労働者を使用する使用者には就業規則の作成および行政官庁への届出義務を課しておりますが、作成義務がない常時9人以下の事業場であっても職場ルールを明文化することで無用なトラブルを避けるためにも就業規則の作成をお勧めしております。給与規定や服務規律に関するトラブルが近年増加傾向にあり、懲戒処分(特に懲戒解雇)を行う場合、就業規則への懲戒事由の記載は必須となります。
就業規則を作成・改定した際は社員説明会を開催することで周知するようにし、その後は休憩室に備える等により「就業規則の内容を知らなかった」と言われないようにしましょう。
固定残業代とはどのようなものなのでしょうか。
一定時間までの残業代を固定給化する制度です。
給与計算時の残業代計算を簡素化するために、ある一定時間までの残業代を毎月固定給として支払う制度です。注意しなければならないのは固定残業代を支払ったからといって追加での残業代が一切不要になるという訳ではありません。当初設定した一定時間を超えた場合は追加での支払いが必要になります。役職手当や営業手当を固定残業代として支給している会社が散見されますが、適法に導入するためには予め就業規則や雇用契約書に固定残業代である旨を明記することが必要です。
有給休暇は何日与えればいいでしょうか。
下表の日数を与える必要があります。
労働基準法上、①雇入日から継続して6ヶ月間勤務している、②全労働日の8割以上出勤している、の2つを満たすと下表のとおり有給休暇が発生します。
雇入日から起算した継続勤務 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 |
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
また、パートやアルバイトには、所定労働日数や所定労働時間に応じて下表のとおりになります。
| 雇入日から起算した継続勤務および付与日数 | ||||||||
週所定労働時間 | 週所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 |
6ヶ月 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 |
30時間以上 | 5日以上 | 217日以上 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
30時間未満 | 4日 | 169日~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
2日 | 73日~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | |
1日 | 48日~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 | |
雇用契約書には何を記載すればいいのでしょうか。
法令上、最低でも以下の項目を記載する必要があります。
労働基準法施行規則では使用者が明示しなければならない労働条件として、次の事項を挙げています。
1. 労働契約の期間
2. 就業の場所及び従事すべき業務の内容
3. 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、並びに労働者を二組以上に分けて交代勤務させる場合の就業時転換に関する事項
4. 賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期
5. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
6. 昇給に関する事項
7.退職手当の支給が適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算と支払いの方法と支払いの時期に関する事項
8. 臨時の賃金等及び賞与に関する事項
9. 労働者に負担させるべき食費、作業用品等に関する事項
10. 安全及び衛生に関する事項
11.職業訓練に関する事項
12.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
13. 表彰及び制裁に関する事項
14. 休職に関する事項
上記1~5までは、従業員に書面を交付して必ず明示しなければならない事項で、6については明示は義務付けられているものの書面での明示までは要求されておりません。7以降は使用者がこの定めをする場合にだけ明示しなければならない事項です。さらに、パートやアルバイトの場合は①昇給の有無②退職手当の有無③賞与の有無を書面で明示する必要があります。
就業規則には何を記載すればいいのでしょうか。
法令上、最低でも以下の項目を記載する必要があります。
労働基準法第89条では、就業規則への記載事項をして以下の11項目を挙げています。
1.始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては、就業時転換に関する事項
2.賃金(臨時の賃金等を除く。以下この項において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3.退職に関する事項(解雇の事由を含む)
4.退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
5.臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
6.労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
7.安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
8.職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
9.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
10.表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
11.以上のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
これらのうち、1~3の事項はいかなる場合でも必ず就業規則に記載します。また、4~11の事項は、定めをおく場合には必ず就業規則に記載します。
なお、これら以外の事項についても、慣例により労働条件の一部となる場合は、その内容が法令又は労働協約に反しない限り任意に記載することができます。
平均賃金はどのように計算するのでしょう?
労働基準法第12条に沿って計算します
平均賃金とは、次の手当を求める際の基準となる金額のことで、労働基準法12条に計算方法が定められています。
1.解雇予告手当
2.休業手当
3.年次有給休暇中の賃金(平均賃金を支給すると定めた場合)
4.災害補償
5.懲戒処分時の減給上限額
平均賃金は、算定すべき事由の発生した日の前日から遡った3ヶ月間(暦日)にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額と定められています。(給与の締切日がある場合は、直前の給与締切日を基準に遡った3ヶ月間)
賃金の総額には、臨時に支払われるもの(祝い金や特別手当など)・3ヶ月を超えて計算されるもの(賞与や期末手当など)を除くすべての手当が含まれます。よって、毎月固定で支給される手当はもちろんのこと、時間外手当や歩合給などの変動する手当・通勤手当などの非課税手当も賃金の総額には含まれます。
賃金が時給・日給・出来高で支払われる場合や欠勤が多い場合は、その期間の総日数で除すと平均賃金が低額になる場合があるため、遡った3ヶ月間の賃金総額を、その期間の労働日数で除した金額の60%が最低保証額になります。
平均賃金<最低保証額 最低保証額を支給する
事業主の都合で従業員を欠勤させた場合は、平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければなりません。この時の休業手当は労働日に対して支給すればよく、休日に支給する必要はありません。
特定社会保険労務士
岡崎 真吾
ご相談者様の立場に寄り添い、親切かつ丁寧な対応をしてまいります。お気軽にご相談ください。